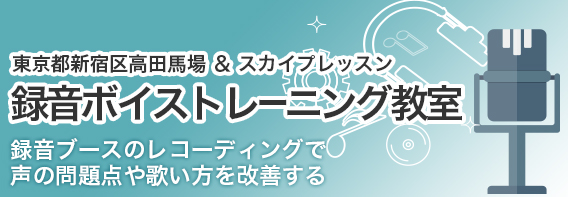DTMや音楽制作を我流で学んでいると「壁」にぶつかります。
壁はいろんなところにあり、僕も幾度となく壁に行く手を阻まれます。
この壁をわかりやすく表現すると「プロのあの音にならない」
我流のアマチュアにはこの原因がどこにあるのか理解できず、わからないので解決できません。
曖昧な判断で問題を解決しようとして、問題をより複雑にしてしまいます。
プロの音を手に入れるためには「特殊なルール」を守ることが必要。
その技術を習得したとき、サウンドの向上は作品のクオリティーに絶大なプラスをもたらします。
DTM教室で短期的にレッスンを受講し、集中して技術やノウハウを盗む方法は、費用対効果が高いと考えざるを得ません。
プロのクリエイターから、直接その技術を教えてもらえるわけですからね。
あなたの作品がプロの作品と似て非なるのは、制作方法が「アマチュアの負のスパイラル」に陥っているからです。
「引き算」の壁
プロの作品を聴いて、何種類の音が同時に鳴っているかを数えてみましょう。
おそらく、同時発音数は10以内でおさまるはずです。
なぜだと思いますか?
音はかさねるほど音質が悪くなるからです。
作っているプロジェクトで、一つのトラックを「ソロ」再生と混ぜた状態で、音の印象をチェックしてみてください。
ソロ再生の方が、音の立体感があるように感じるはずです。
音は空間を鳴らして響きを表現します。
つまり鳴らす空間に音が少ないほど、本来の音色に近いものになります。
トラックが重なると「マスキング」に代表する、同じ周波数帯が干渉し合い、個々の音を不明瞭にする原因となります。
なぜいたずらに音を増やすのか?
- ①トラック数が少ないと、しょぼく物足りなく感じる
- ②トラック数が多い方が、バランスをとればなんとかなりそう
トラック数が過剰に増えてしまうDTMerの発想は大体こんなところです。
①トラック数が少ないと、しょぼく物足りなく感じる
プロはピアノ一本でも聴かせられるのに、自分が打ち込んだピアノはパッドやリズムを足さないと聴けたものではありません。
演奏力の問題もありますが、原因は「良い音色」が作れていない場合がほとんどです。
子供の下手くそな歌に心をゆさぶられることってありますよね?
演奏は内容が全てではないのです。
音楽制作には「良い音色」を作るための特殊な手法とノウハウ、ルールがあります。
どんな教本にも書いていない裏のルールについて、独学DTMerは自分で検証し、学ばなければいけません。
②トラック数が多い方が、バランスをとればなんとかなりそう
音楽はバランスによってその意味が変わります。
その方向性を他者にゆだねるというのは、作品において「自分は責任をとりません」と言っているのと一緒です。
アレンジでそんな責任放棄をしていても、ミキシングで自分が苦しむだけです。
ダビングやトラックをレイヤーする手段はアレンジの中で非常に効果があります。
しかしそれは「音を重ねる必要があるシーン」に限ります。
作品や音がボケているのなら、それはアレンジの段階で解決する必要があります。
ダメ音が産み出す「負のスパイラル」
音を増やす時に大事なことは「誤魔化すために」ではなく「もっと良くするために」である必要があります。
マイナスをゼロ、ではなく、ゼロをプラスにするために音が存在しなければなりません。
- ①悪い例)ピアノの音がしょぼいから、パッドの音を足してフォローする
- ②良い例)ピアノの音が良くないから、音源や音作り、演奏内容を見直す
①では、演奏内容は改善されないばかりか、音場を不要に塗りつぶすトラックが追加されます。
②では、内容が見直され質が上がり、かつ余計な音が追加されず、他の音が追加される余地が残ります。
上記は一例ですが、岐路での判断はものを作る上での考え方の本質が浮かび上がってきます。
①を繰り返していると、トラック数が多くて内容の悪いアレンジが出来上がります。
②は音や演奏内容の「質」を問われるので、悩むシーンは増えますが、感性を鍛える方向に進んでいます。
作品の質は、音の多さではありません。
ひとつひとつの作業や音を洗練することで、あなたの作品はプロレベルに一歩近づきます。
「良い音」とは?
音楽と同じように音にも好みがありますので「良い音」は時代や人によって変化します。
ここでは音楽制作における「良い音」を以下のように定義します。
- ①質感がよく、単品で聴いても心地よい
- ②音量や周波数のバランスが良い
- ③ダイナミクスが正常に機能している
①質感がよく、単品で聴いても心地よい
音はレイヤーしてごまかすのではなく、心地よい音を重ねて作り上げるべきです。
単品で聴いて魅力を発揮できない演奏や音色は、内容そのものに問題があります。
音作りや演奏内容を精査して、魅力のあるトラックを作りましょう。
②音量や周波数のバランスが良い
演奏の段階でバランスに配慮することはもちろんですが、コンプ、EQ、アナログ系機材を使った調整が必要です。
音量はオートメーションやコンプで、周波数はEQやアナログ系の倍音付加によって、それぞれをバランスの良いソースに仕上げます。
バランスの良いソースは埋もれにくく、エフェクト乗りも良い扱いやすい素材になります。
③ダイナミクスが正常に機能している
音はアタックとリリースで構成されており、このバランスが悪いと、不要なピークが生まれたり、アタックが埋もれてスピード感のない仕上がりになりがちです。
周波数が問題を起こしているときはEQで、コンプやトランジェントでアプローチするのが通常です。
リバーブでアタック成分を補佐する方法もありますが、リバーブは不要に音場を埋めやすいので、素材の段階で問題が解決していることが望ましいです。
音色や演奏に固執すれば「本物」が見えてくる
DTMはなんでもできるツールに見えがちですが、アナログでできてデジタルでできない音はむしろ多いと言えます。
打ち込みを緻密にやるより、ざっくり弾いたギターなどをマイク録音した音の方が、雰囲気があったりするから不思議です。
複雑な作曲やゴージャスなアレンジにとらわれず、目の前にある「音」にこだわってください。
今まで出せなかった音色が出せたとき、きっと新しい創造への扉が開くはずです。