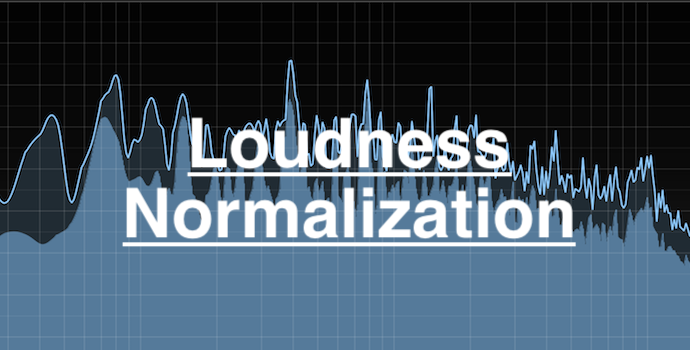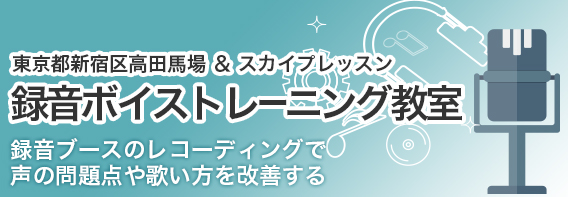「DAWによって音質が違う」
誰もが一度は耳にしたことがある風説です。
最近のDAW業界は成熟して、どのDAWもかなり音質が良くなりましたが、今でも「Logicは音が悪い」「Protoolsは音がいい」諸説を根拠なく信じる人が多いです。
- なぜDAWによって音質が変わるのか?
- 「PAN」の落とし穴と正しい使い方
今回はこの2つについて解説します。
なぜDAWによって音質が変わるのか?
- プレイバックエンジン
- ステレオ音源の扱い(インターリーブ、スプリッド)
- 「PAN」の扱い
- ディザリング
音質の違いは大きく分けてこの4つに分類できます。
これはDAWごとのソフトやプラグインによる差ではなく、同じ音源やプラグインをボリュームとパンのみで構成し、書き出した際の音質差について述べています。
順番に、その内容を解説します。
①プレイバックエンジン
デジタルオーディオは情報ですので、どんな環境においても情報としての誤差はありません。
しかし、オーディオインターフェースやスピーカー、ヘッドホンで再生音が変わるのは、情報を処理してアナログ音声にする手法が、メーカーや製品ごとに異なるからです。
DAWの内部処理にも各ソフトごとに音声処理に差異があり、これが音の違いにつながります。
質の良い悪い、でなく「傾向の違い」と捉えるべきでしょう。
また、オフラインバウンスでは演算で音声処理を行うため、同じDAWでもプレイバック時と、書き出し後で音質に違いが生じることがあります。
聴いている音をそのままオーディオ化したい場合、リアルタイムバウンスを行うか、ADDAで外部に出力した音を外部機器で収録する方法があります。
②ステレオ音源の扱い(インターリーブ、スプリッド)
- インターリーブ - ステレオ音源を一つのステレオとして扱う
- スプリット - 左右にパンを振り切った二つのモノラルとして扱う
プロツールスはステレオ音源を昔からスプリットとして扱いますが、大抵の個人向けのDawはインターリーブを使用しています。
これは個人ユーザー向けに操作を簡易化する目的からです。
スプリッドは二つのモノラルのPANの幅を調整することによって「ステレオ感」(狭める、広げる)を調整することができます。
この問題は解決されつつあり、Logicでは「ステレオパン」が導入され、ステレオ音源をスプリット同様に扱うことができます。
また、ステレオイメージ系のプラグインでは「width」のパラメーターで広がり方を調整することが可能になり、インターリーブのデメリットは克服されたと考えることができます。
重要なのは「ステレオ感の調整」という概念がある人とない人が同じ作業をした場合、クオリティーに差が生まれてしまうことです。
ステレオ音源をどう扱うか、よりもユーザー側がDAWやステレオ音源に正しい認識をもつことが必要です。
③「PAN」の扱い
まずパンニングには「Pan Low」という設定値があります。
これは、左右にパンニングしたときと比べ、センターに配置した音源が大きく聞こえてしまう事を考慮し、「センターに配置した音の音量を下げる」という設定です。
CubaseやLogicが「-3db」なのにくらべ、Protoolsは「-2.5db」が初期設定です。
たまに「同じ設定値でDAWの音質差を検証する」という趣旨のブログなど見かけますが、①はまだしも、②や③の設定値が異なる事を考慮すれば、音に違いが生まれるのはむしろ当たり前で、検証方法自体がナンセンスだと言えます。
④ディザリング
簡単に言うと、ディザリングとはビット深度における「エンコーダー」です。
ビット深度とは「音の大小における解像度」。
つまり音量やダイナミクス表現をどれだけの解像度で表現するか、という値です。
「bitcrusher」でビット指数を上下すると、サウンドの関係性がわかります。
最近のDAWは、プロジェクト設定値が24bitでも、内部処理は32bitが珍しくありません。
CD規格は16bit/44100hzですので、約半分のビット深度に間引く必要があります。
書き出しの際に「ビット深度をどのように間引いていくか」を判断するのが「ディザリング」
選択するアルゴリズムによって音質に変化が生じる、という点ではプレイバックエンジンとノリは同じです。
DAWの苦手分野をフォローする
DAWの音質差については前述の通りですが、単純に音質が一番良いDAWを使うべきかといえば、疑問が残ります。
私はLogicの操作性やエフェクト、長期的なアップデートを行ってくれるところが好きですし、CubaseはHalionが音源として協力で、 扱いやすいプラグインが多くFrequencyなど強力なソフトも追加されました。
Studio Oneは音質に定評がありますが音源が多様でなく、FL Studioも人気ですがEDMに偏っている側面があり、一長一短です。
「どのDAWが良いか?」を考えるのではなく、作るものにあった特性のDAWを使い分けたり、DAWの不足部分を外部のソフトによって補填するのが望ましいです。
「PAN」の落とし穴と正しい使い方について
パンとボリュームによって私たちが表現するのは「音の位置」だと考える事ができます。
これは写真で考えると、メインの被写体に対しての横位置と距離です。
「音を左奥に配置しよう」と考えた時、PANを左に振って音量を下げるだけでは不足があります。
これがカメラの場合、被写体の後ろにある景色は適度にピントが外れ、輪郭がぼやけます。
色彩の細かさもなくなり、要するに後ろにいくほど「劣化」していきます。
音で考えると「遠い音ほど位相がぼけ、ダイナミズムが減り、音が痩せる」と考えて処理すると、イメージと近い距離表現を作り出す事ができます。
パンとボリュームに加えてコンプ、EQ、コーラスといった処理が必要です。
音をうまく劣化させることができると、ソースのボリュームを大きく保つことができます。
- パンを大きく振る時は「ダイナミズムを減らし、ステレオ感を狭める」
- ステレオ感が響きに大きく影響するソース(ピアノなど)はセンター付近に配置
- パーカッションなどのダイナミズムに干渉するソースは、パンを大きく振らない
私はミックスの時に、配置に対して上記のルールを定めています。
要約すると「センターから離れているほど音像を劣化させる」ということです。
理想のパンニングなら「Cyclic Panner」一択
重要なソースはセンターに近い位置に配置すべきですが、ここで次の問題が発生します。
このままでは、センターに音が集中し、音圧が稼ぎにくくなります。
ふまえると、音のおいしい部分を殺さずに、音をパンの外側や、サイド成分に割り振る、という手法が求められます。
A.O.M「Cyclic Panner」は、その問題点の多くを容易に解決することができます。
 「Cyclic Panner」では「Axis Transformation」という処理を定位調整に採用。
「Cyclic Panner」では「Axis Transformation」という処理を定位調整に採用。
以下のメリットがあります。
- 左右に大きくパンを振りつつ、ステレオ音像を維持
- パンの振り切りより外側「サイド成分」に音を配置できる
- 「LPF」を用い、「パンと反対側のチャンネルに低域通過」を簡単に実現
使ってみるとわかりますが、大きく振っても音像に違和感がなく、ステレオ感も崩れにくい。
サイド成分に音を配置することができるので、センター成分を減らしサウンドフロアーを広く活用できます。
また「LPF」は特筆すべき効果があり、配置した反対側に低域を逃してステレオ化するので、低域が持つ質感やダイナミクスを殺さずにソースを活かすことができます。
要するに「なんでこれが標準装備されてないんだ!」というプラグイン。
私は自分の制作環境においては、DAWのパンは使わず、すべて「Cyclic Panner」で定位を作っています。
サウンドフロアをはばひろく使うことの重要さ
デジタル音声には「音量、ダイナミズム、位相、周波数、定位(LR、Mid/Side)」の5つの概念があります。
その全てで重要なことは、偏らずバランスよく構成すること。
プロの作品では、大きくパンが振られているミックスや、LRどちらかのみで鳴っている音、がよく用いられます。
参考にして自分で試してみると、音痩せしてしまってイメージ通りにならないことがほとんどです。
「Cyclic Panner」は、ミックスにおける定位の大きな問題を簡潔に解決してくれます。
ミックスに広がりがなく、音が飽和して悩んでいる方は、ぜひ試してみてください。